1~4年生 球技大会(10月1日)
美風・体育委員会主催の球技大会、第3回目は1~4年生のドッジボールを行いました。
司会進行・運営は、5~6年生が行いました。


どのチームも盛り上がる試合でした!



他のチームの応援をしています。




5~6年生の係の児童も、自分の役割をしっかり果たしてくれたおかげで、前期ブロックの仲がより深まる、楽しい球技大会になりました!

美風・体育委員会主催の球技大会、第3回目は1~4年生のドッジボールを行いました。
司会進行・運営は、5~6年生が行いました。


どのチームも盛り上がる試合でした!



他のチームの応援をしています。




5~6年生の係の児童も、自分の役割をしっかり果たしてくれたおかげで、前期ブロックの仲がより深まる、楽しい球技大会になりました!
7年生と9年生は柔道の授業がありました。
まずは7年生です。
受け身の練習をしました。
前受け身は、肘から手までを床につけて受け身を取ります。
言われたポイントを意識してできました。


後ろ受け身です。
畳をバン!とたたく音がそろってきれいでした。


横受け身です。
手は体から45度の位置でたたくこと、もう一方の手は帯をもつことを意識してできました。

前回り受け身を練習しました。
7年生はまだ2回しか授業をしていませんが、前回り受け身ができるようになりました。



7年生は受け身が上手にできたので、固め技に進みました。
けさ固めと横四方固めを習いました。




固め技のやり方を一通り確認した後、抑えられた人が逃げてみました。
「絶対抑えるぞ!」「逃げるぞ!」と強気で、勝負を楽しみました。
次は9年生です。
9年生は、小内刈り、大内刈り、体落とし、払い腰の4つを練習しています。
それぞれの立ち技の、打ちこみ練習をしています。

釣り手がぐっと上げることを意識しています。





足を外側に出すことがポイントになると教えてもらってから、すぐ実践していました。


9年生は立ち技に挑戦していますが、相手の安全にも気を付けながら練習することができています。
体落としと払い腰は今日初めてやってみましたが、「どこに足を出す?」「難しい!」と言いながらも繰り返し練習し、スムーズにできている人もいました。さすが9年生!
今日は7年生と9年生の授業でしたが、8年生でも立ち技の練習を始めています。
どの学年も、ペアで協力しながら技の習得を目指しています。
最後の実技テストに向けて、頑張っていきましょう。
2月13日(木)1限 理科
今日は、堆積岩の見分け方についての学習です。
いくつかの石を、実際に見て触って確認しながら見分けていきます!

最初に「れき岩」「砂岩」「泥岩」を探します。
「れき岩はこのゴツゴツした石だと思う!」
「砂岩と泥岩の見分け方が難しい…」

 「この黄土色の石は砂っぽい、でもこの灰色の石も粒が細かいよ」
「この黄土色の石は砂っぽい、でもこの灰色の石も粒が細かいよ」
観察をしながら細かい特徴に目を向け、3種類の石を見分けることができました。
続いて、「石灰岩」「チャート」「凝灰岩」を探します。
大きな画面で石の特徴を確認しました。
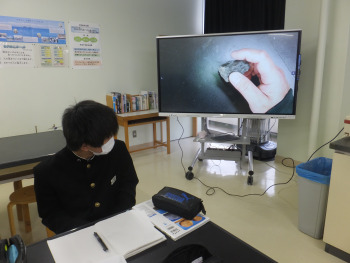
以前学習した「火成岩」の復習も行い、違いを改めて確認しました。
いつもよく見ている石ですが、新しいことが分かると、とても興味深いですね。
さて次回からは、いよいよ、みんなが楽しみにしている「化石」の学習に入ります。
体育の時間に、柔道の学習をしました。
今日は立ち技を中心に練習に行い、
「大内刈り」「小内刈り」「体落とし」「大腰」を習いました。





「大腰」は、今日初めて習った技です。
自分の腰に相手の身体を乗せることが難しく、苦戦していましたが
「1、2、3」と口ずさみ、一つ一つの手順を確認しながら練習に取り組んでいました。



この調子で、立ち技をマスターできるように頑張りましょう!
9月19日(木)
宿泊学習を来週に控えている中期ブロックで
しおりの読み合わせをしました。
全員で、2日間の日程を確認しました。

その後、野外炊飯のグループごとに分かれて「ピーラー」や「たわし」等の持ち物を分担しました。


皆で話をするうちに、だんだん実感が湧いてきたでしょうか。
明日は荷物点検と係の打合せ、整列の練習をします。
6限 多目的ホールに、中期ブロックの児童生徒が集まりました。

今月25日、26日に行う「宿泊学習」に向けた初めての集会です。
今年度も能登青少年交流の家で活動をします。
宿泊学習の目的と、青少年交流の家でのルールについての説明を聞いた後、
5つの班に分かれ、係を決めました。

班長を中心に、話し合いながら決めていました。
最後に、1日目に実施するレクリエーションについて、
7年生から説明がありました。

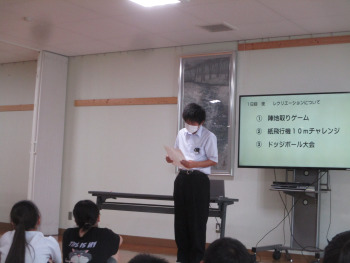
今回初めての宿泊学習となる5年生も、真剣に話を聞いていました。

当日まで、何度か中期ブロックで集まって準備をします。
よい活動になるよう、学年の枠を超えて協力ながら取り組んでいきましょう。
今日は、後期課程の生徒で応援の隊形を確認しました。練習の最後に、実際に応援の通し練習を行いました。今日の反省を生かし、来週は応援の完成を目指します!
また、初めて和太鼓を使って練習してみました。





