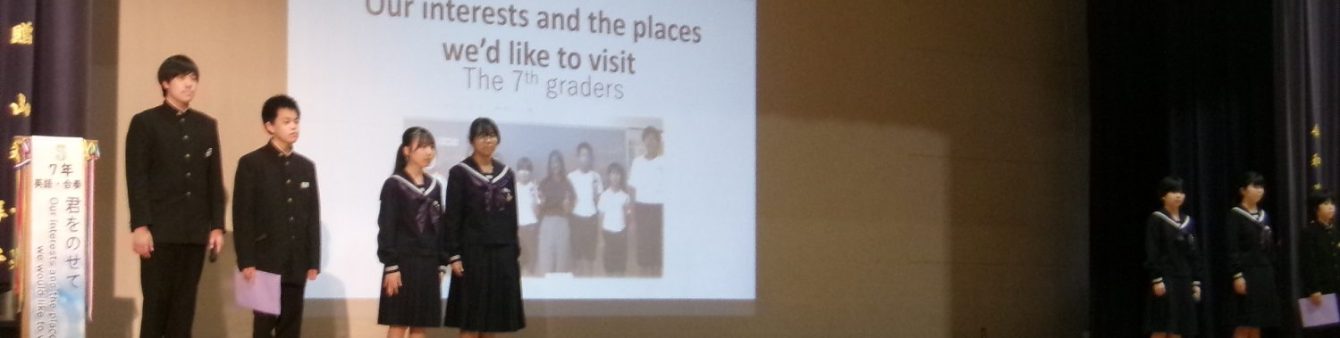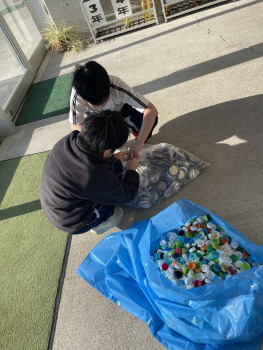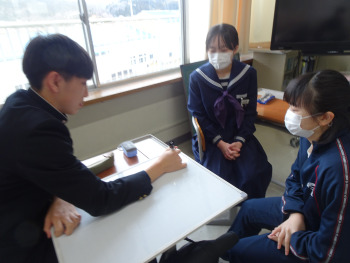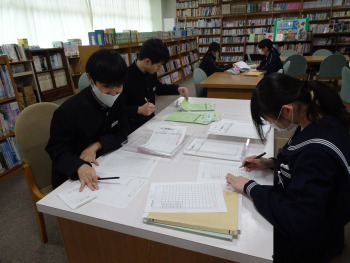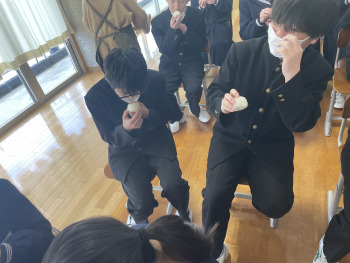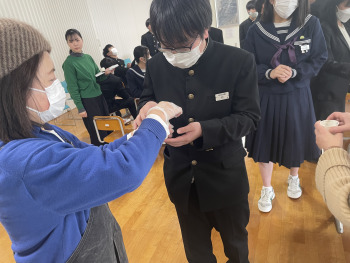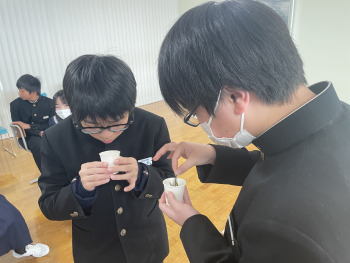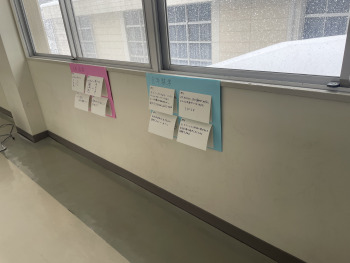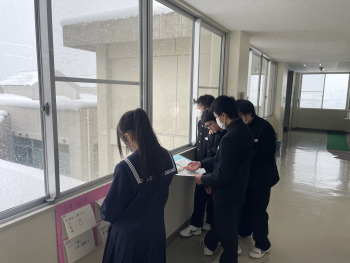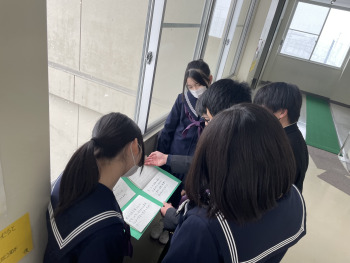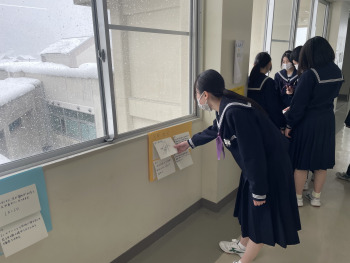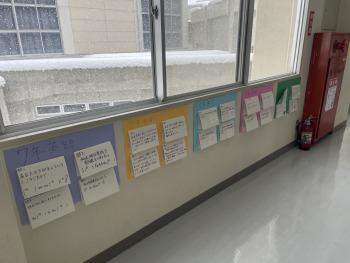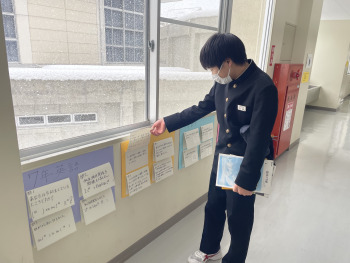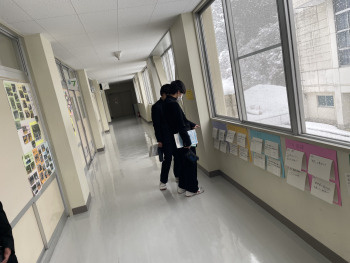前期課程 修了を祝う式、お祝いコンサート(3月14日)
昨日の卒業証書授与式に引き続き、今日は前期課程修了を祝う式を行いました。
朝から、すばらしい晴天。修了生をお祝いしているかのようです。

新しい制服の修了生たち。
笑顔で、元気よく登校しました。


式が始まりました。
校長先生から、前期課程修了証書をいただきました。
大きな声で返事をし、きびきびとした動作で、堂々とした態度でした。




校長先生の式辞では、証書に書かれている二つのことについて話されました。
一つ目は、家族の愛情や思いが込められた「名前」、二つ目は、家族の宝物として「生まれてきた日」です。
そして、「未来の自分は、今の自分がつくる」という言葉とともに、後期課程進級に向けて、誇りと自信をもって、新しいことに取り組んでほしいと話されました。

「お祝いのことば」では、5年生の代表が言葉を贈り、来年度はリーダーとしての役割を引き継ぐことを約束しました。


修了生の「決意の言葉」では、一人一人が将来なりたい職業や、後期課程で頑張りたいこと等を、発表しました。
「パティシエになりたい」
「歯科医師になりたい」
「困っている人を助けられる人になりたい」
「後期課程では、勉強や部活を頑張りたい」
等、4月からの決意をしっかりと述べました。






修了を祝う式の次は、楽しみにしていた「お祝いコンサート」です。
今年度は、セリオラ・クインテットの五人の皆様をお迎えしました。
コンサートのプログラムには、クイズあり、寸劇あり、校歌の合唱あり、6年生のパーカッション参加ありの、盛りだくさんのメニュー。
楽しい1時間が、あっという間にすぎました。




お祝いムードの中、後期課程に進む気持ちの準備ができた1日でした。
6年生のみなさん、月曜日からまた元気に登校し、6年生の教室でたくさん思い出をつくりましょう。