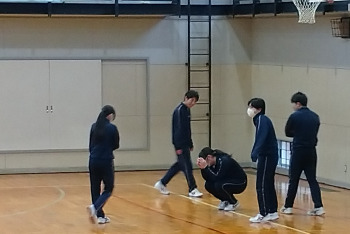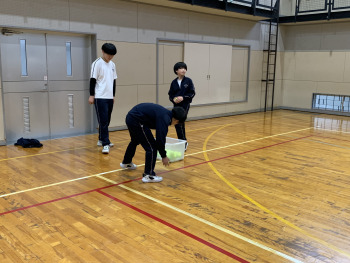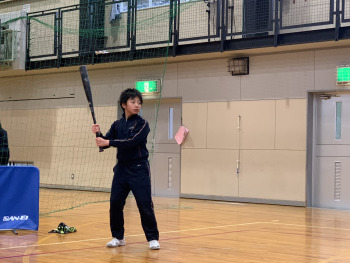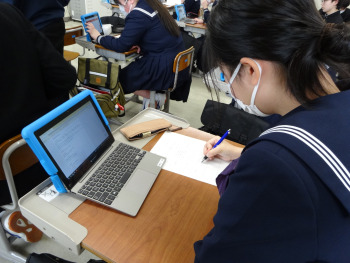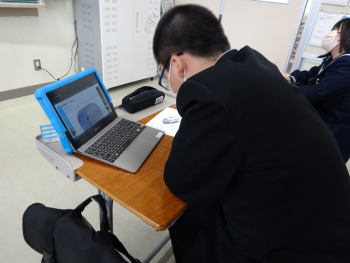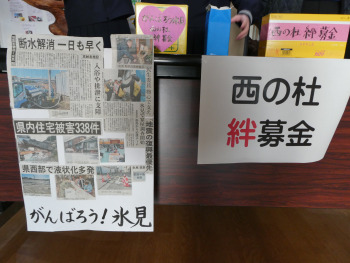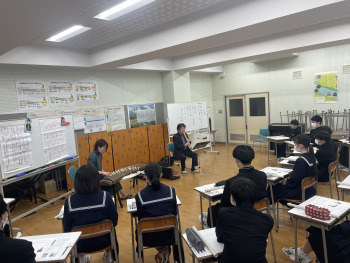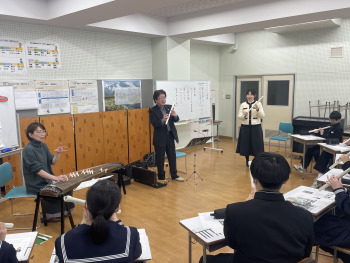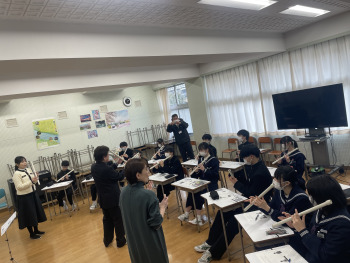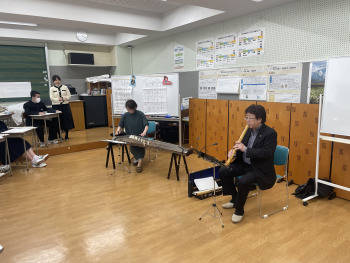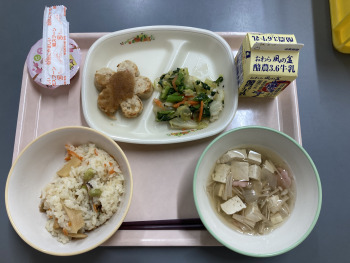2,3年生 九九名人になる!!(3月6日)
今週の昼休みは、毎日、校長室に来客があります。
そのお客さんは・・・
2年生と3年生です。
今、2,3年生は、九九検定を行っているのです。
今週の月曜日から、覚えている九九を校長室で発表しています。


挑戦する段を自分で決めて、一人一人が、校長先生の前で言います。
すらすらと言えたり、
少し詰まったり、
子供たちは、少し緊張しながらも、各段の「上り」と「下り」に挑戦しています。


「速く言います」
「ゆっくりとしか言えないけど、頑張ります」
など、自分の気持ちを伝えながら、頑張る子供たち。
「はい、合格です」と言われると、嬉しそうに、合格した段にシールを貼っています。
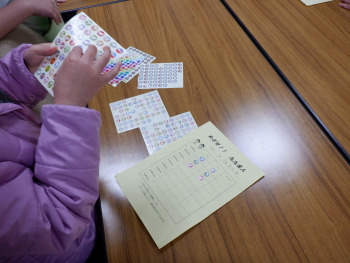
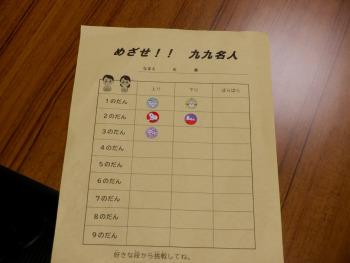
全ての段の「上り」と「下り」が終われば、「ばらばら」に挑戦し、「ばらばら」に合格すれば、
「九九名人」になります。
「早く認定証がほしいな」「明日も来ます」と言いながら、校長室から出て行く子供たちの姿は、とてもほほえましく、頑張ろうという意欲に満ちています。
2,3年生の皆さん、「九九名人」を目指して頑張りましょう!!