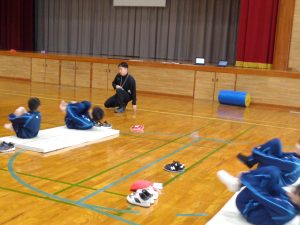滑る楽しさを味わったスキー学習
15日に4~6年生がスキー学習を行いました。
スキーが初めての子供たちもいましたが、
インストラクターの方の指導を受けながら上達していきました。
初めてのリフトは怖かったけれど、景色がよかったそうです。
経験のある子供たちは、ゴンドラに乗って上まで行き、
滑っておりてくることができました。










自分の目当てに向かい頑張り、滑る楽しさを味わうことができた子供たち。
全員無事に、けがなく学校に帰って来ることができ、安心しました。
どの子供にとっても貴重な体験ができた一日でした。