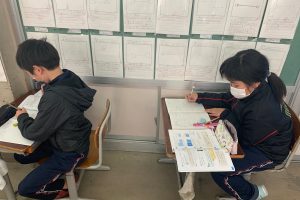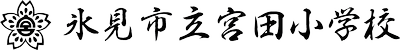平成16年度から、厚生労働省の主唱により、11月を「児童虐待防止推進月間」として、児童虐待防止のための広報・啓発活動が行われています。
この機会に、萩生田文部科学大臣から児童虐待防止に向けてのメッセージが発信されました。
次のとおりです。
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
保護者、学校関係者、地域の皆さまへ
「児童虐待の根絶に向けて~地域全体で子供たちを見守り育てるために~」
11月は児童虐待防止推進月間です。
子供たちへの虐待は、児童相談所の相談対応件数が増加するなど、依然として極めて深刻な状況です。今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響から、生活不安やストレス等に伴い、児童虐待のリスクが高まることも懸念されています。児童虐待により子供たちが傷つき、亡くなるようなことは、何としても無くさなければなりません。
虐待は、殴る、蹴るといった身体的虐待だけではありません。言葉で脅す、無視するなどの心理的虐待、子供を残して外出する、自動車の中に放置する、食事を与えないなどのネグレクトや性的虐待もあります。いずれも子供たちの心身に深い傷を残します。
保護者の皆さま、大切なお子さまの健やかな成長のため、「虐待はしない」と誓ってください。子育てに不安や悩みがある時には、身近な人に相談したり、自治体の相談窓口等を頼ってください。
学校関係者の皆さま、日頃から子供たちと接する中で、児童虐待と疑われる事案に気付いた際は、速やかにチームとして対応し、市町村や児童相談所に通告するとともに、関係機関と連携して対応してください。
地域で子供たちと接する皆さま、是非、子供たちの様子に関心を持って見守ってください。日々の活動やつながりの中で児童虐待と疑われる事案に気付いた際は、最寄りの児童相談所に繋がる全国共通ダイヤル「189」(“いちはやく”)に相談・通告してください。
児童虐待の防止には、家庭・学校・地域が一丸となって子供たちを見守り、育てることが重要です。文部科学省としても、関係省庁とともに取組を推進してまいります。皆さまの御理解と御協力を心からお願い申し上げます。
令和2年11月
文部科学大臣
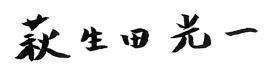
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
もし、身の回りで、お気付きの点がありましたら、学校へお知らせください。