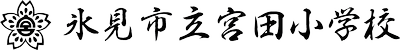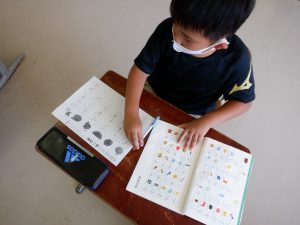8月が終わります
8月31日(月)
今朝の、1年生の教室のベランダです。
グリーンカーテンとして育てているゴーヤの様子が変わっています。


緑のゴーヤの中に、とても鮮やかな黄色のゴーヤが。
触ると、ぽこぽこします。
「割ったら、中は赤いがいぜ」
「緑のゴーヤは苦いから、ぼくは食べられない」
「わたしは、好き。おいしいかったよ」
「え。これ食べられるの」

「一番、長いつるは、2階に届いているよ」
「3階までいったら、どうしよう」
「4階までいったら、どうしよう」
「あれ、宮田小学校に4階って、あったっけ」
朝のベランダでの、ほほえましい会話は尽きません。

1年生が、2学期からも世話を続けているアサガオには、茶色い種ができてきました。
3年生が育てているホウセンカは、花が散ったところに面白い形の種が並んでいます。

気温が高い日が続き、残暑はいつまで続くのかとうんざりしている間にも、
植物は、着実に実りの秋を迎える準備をしているようです。

季節の変化を見付け、伝え合うことができる子供たちの感性を
大切にしたいと思います。