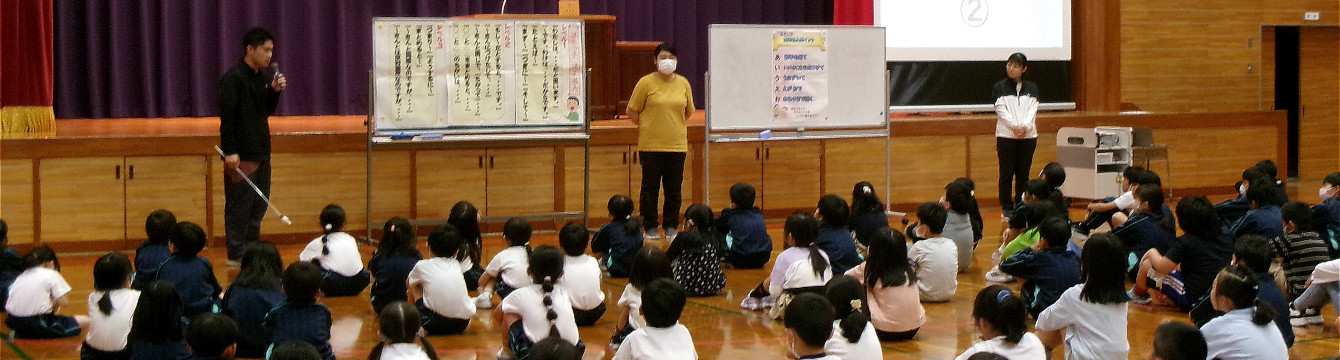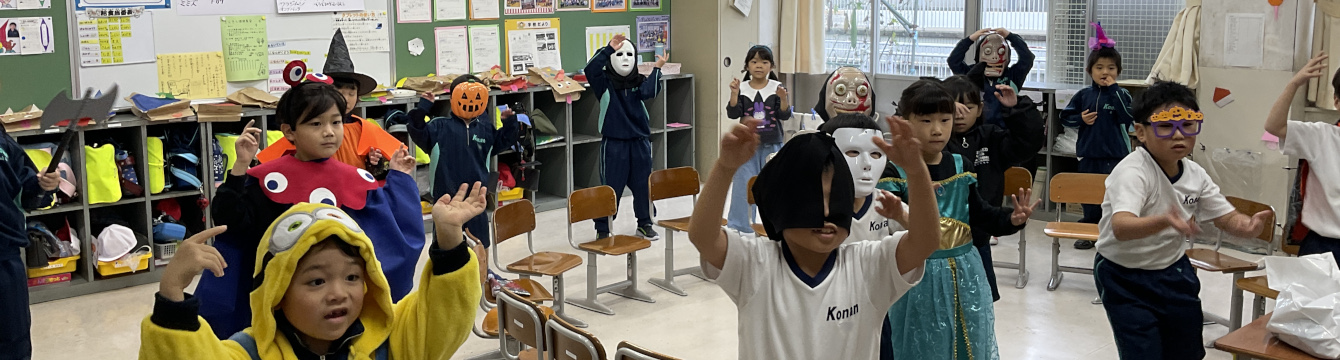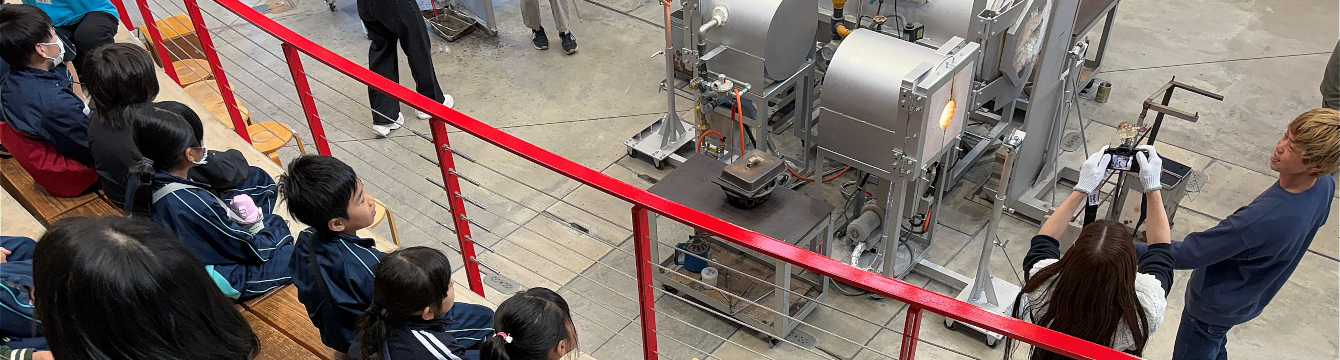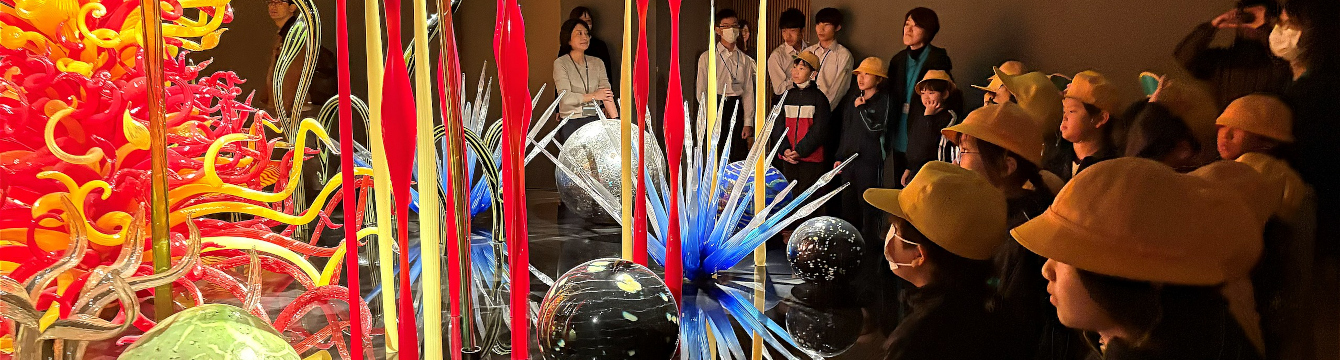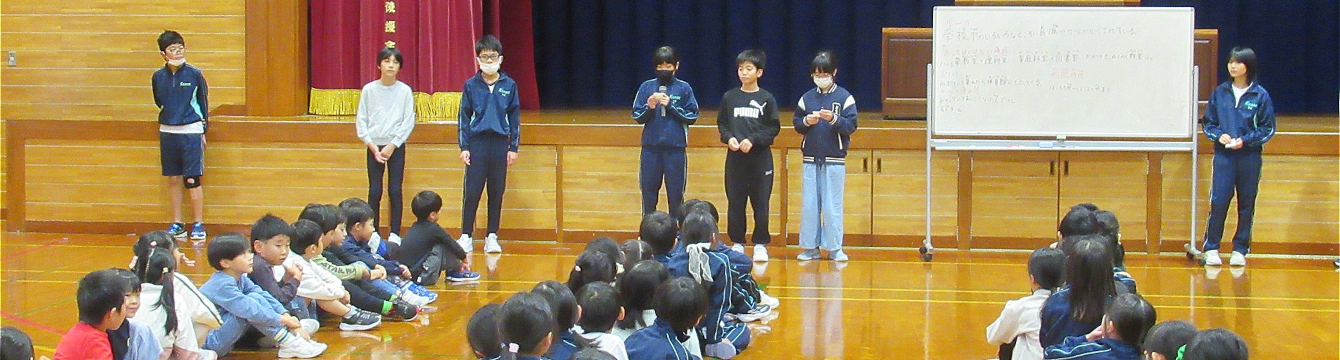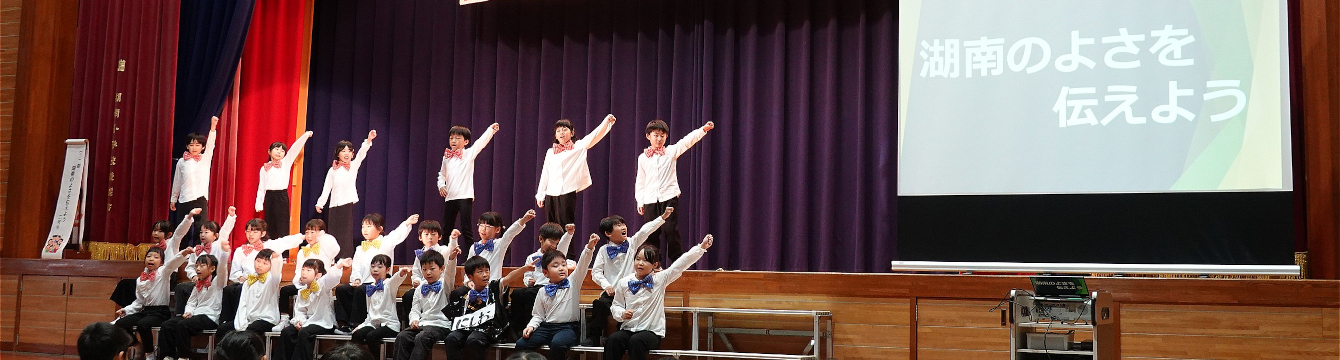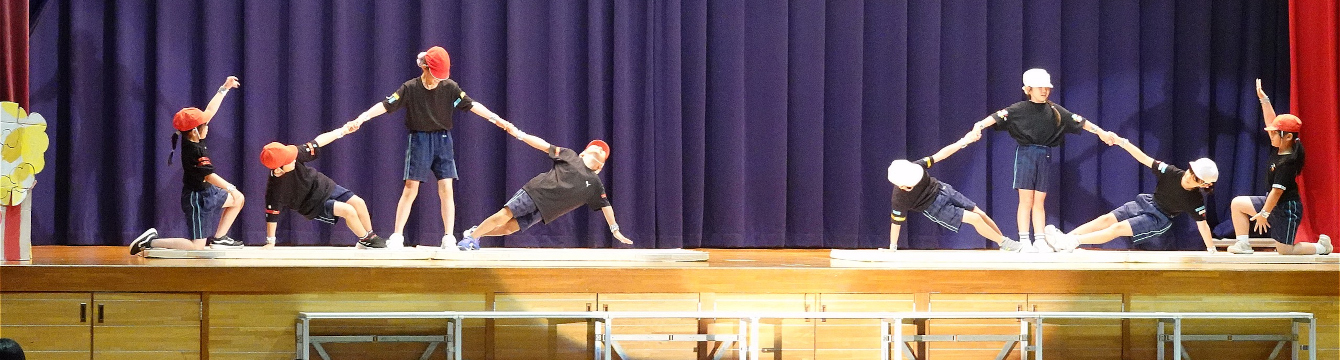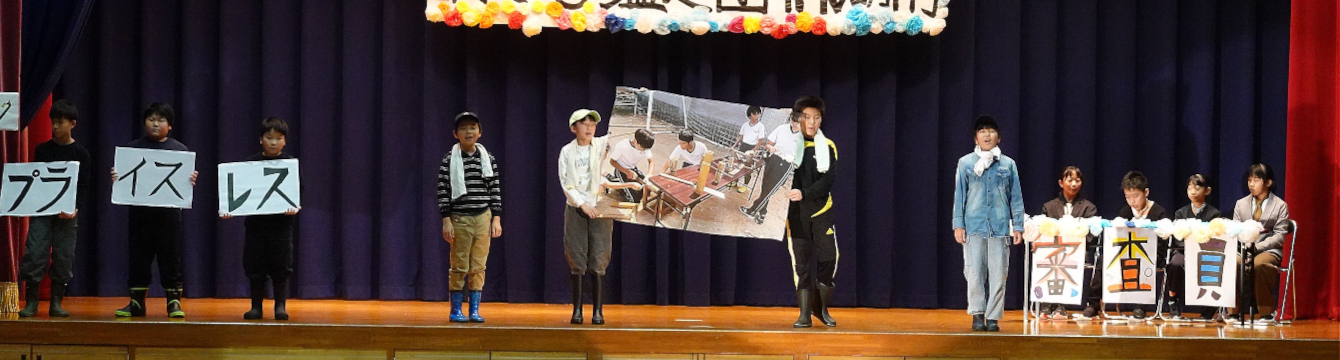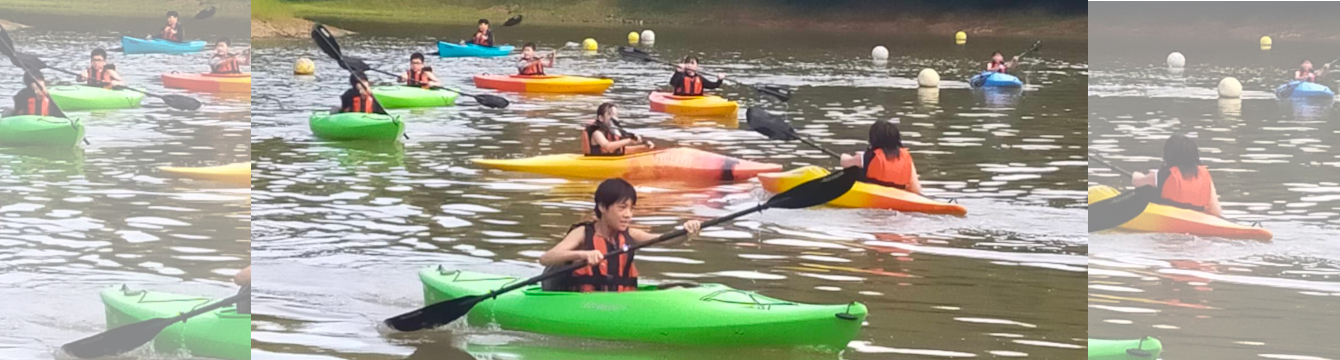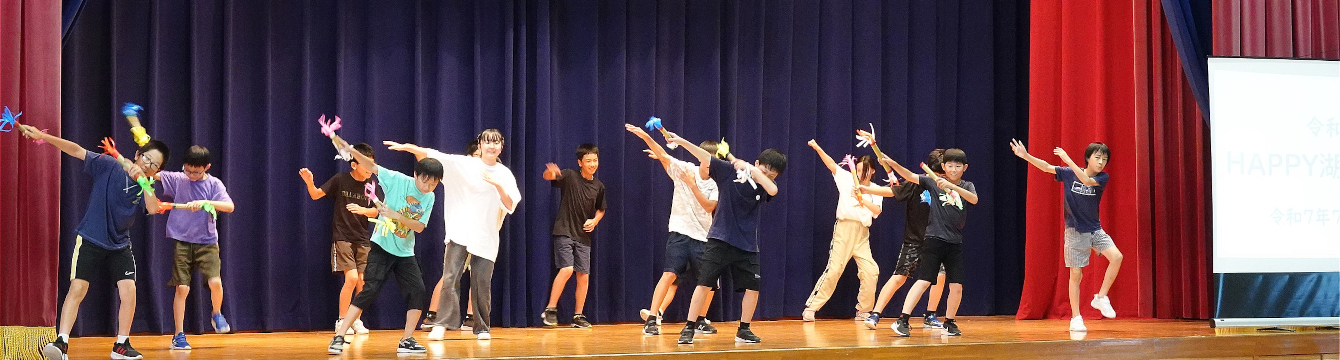6月 5学年おたより
6月 6学年おたより
こども自転車安全運転講習(4年生)★ 6月2日
5時間目、こども自転車安全講習があり、仏生寺駐在所の樋上巡査長が来校されました。
「命はひとつ」。安全に自転車に乗ることのお話の後、自転車の発進から停止まで、一人一人の
自転車の乗り方を見て、ご指導いただきました。子供たちは、真剣な表情で自転車に乗っていました。
ありがとうございました。








環境浄化センターで学びました(4年生) ★ 5月30日
4年生は、社会で上下水道について学んでいます。
30日には、氷見市環境浄化センターを見学しました。


浄水場や下水処理場の仕組みや工夫を学ぶことができ、有意義な時間となりました。
朝の様子(畑の水やり)★ 6月2日
子供たちは、登校したらすぐに畑の水やりに行きます。
ぐんぐん成長する野菜やヒマワリを観察しながら、友達と楽しそうに会話しています。
「キュウリの葉っぱは、地面につかない方がいいよ」と、3年生が2年生に教えてあげる姿も
みられました。やさしい湖南子です。
また、草むしりにも一生懸命に取り組んでいました。








小中合同資源回収 ★ 6月1日
早朝より、小中合同資源回収を行いました。
雨が降らず、無事終えられることができました。
湖南小学校執行役員、地区役員、学年委員、十三中学校育友会役員のみんさんが中心となって、各地区
よりたくさんの資源を回収していただきました。
湖南小学校のグラウンドには、十三中学校の生徒さんが、進んで荷物を運び出したり、コンテナに入れ
たりするなど、頼もしい姿を見せてくれました。
ご協力いただき、本当にありがとうございました。






















プラグ苗の植え付け ★ 5月30日
環境委員の子供たちが、昼休みにプラグ苗の植え作業を行いました。
500本以上の苗をみんなで協力しながら、手際よく丁寧に植え付けしました。
一生懸命に働く環境委員の子供たち。さすが、湖南子!











アクションプラン ★ 5月30日
今年度のアクションプランについて、先生方が劇を交えて子供たちに説明しました。
アクションプラン1・・・思いやりのある子供の育成
「自分で決めた目当てでの挨拶や相手を思いやる言動をしている」と評価する児童が80%を超える。
アクションプラン2・・・対話力の育成
「授業中、伝える内容や順序等を考えて、相手に分かりやすく話している」
「授業中、相手の伝えたいことを考えながら聞いている」
2つのアクションプランについて、子供たちが理解できるよう、具体的な場面や目当てとすることにつ
いて伝えました。
「なりたい自分」に向けて頑張る湖南子を、これからも支えていきます。


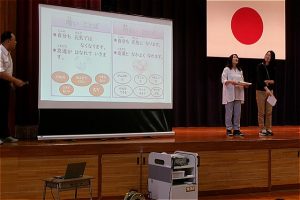


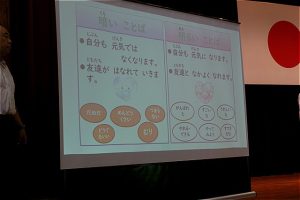
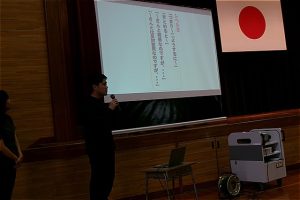
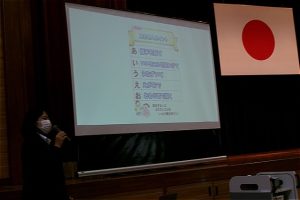
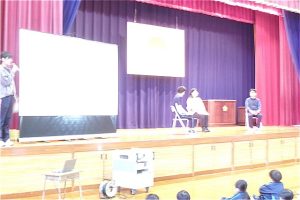















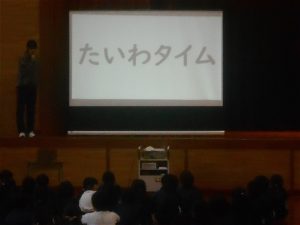

2年生 図画工作科 ★ 5月29日
2年生は、図画工作科「光のプレゼント」の学習で、赤、青、黄、緑色等の光を通すセロファン紙を自
分の好きな形に切り取り、透明の台紙に貼り付けて、作品をつくりました。
今日の図画工作の時間には、グラウンドに出て、太陽の光に当てて映し出し、様々な見え方や感じ方を
楽しみました。
友達と作品をくっつけると、どのように映るのか、楽しそうに試していました。



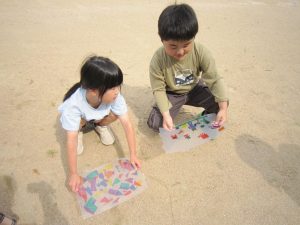


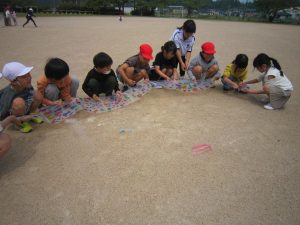
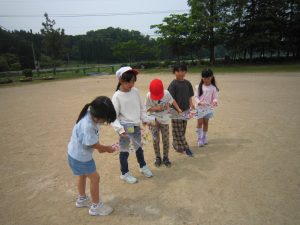
国語科の学習(4年生)★ 5月28日
4年生は、国語科「アップとルーズ」(説明文)の学習をしていました。
「アップ」と「ルーズ」と対比しているところを本文から見付けて話し合っていました。
「対比」の意味を確認し、比べている叙述を探してました。

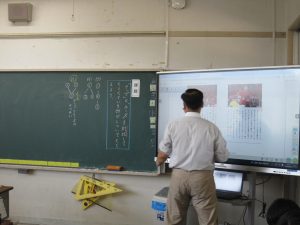


6月 行事・下校予定表
給食だより 6月号
学校だより 5月 第2号

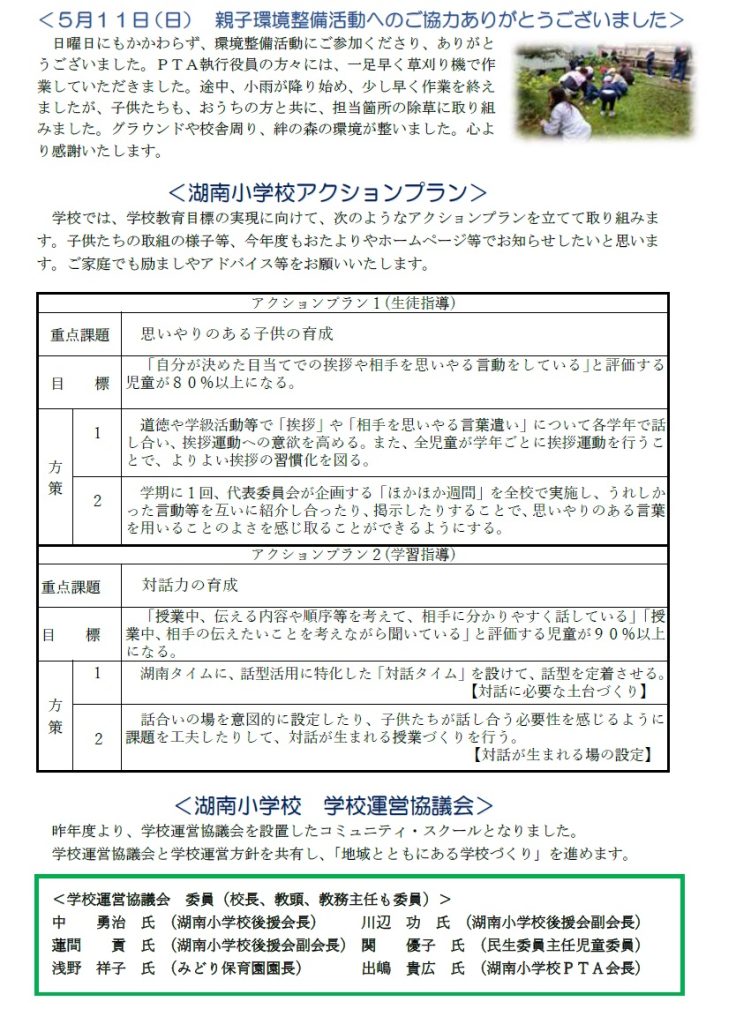
理科で消化について学びました!(6年生) ★ 5月27日
6年生は、理科の「人や動物の体」の単元で、呼吸・消化・血液の流れ等について学習しています。
今日は、「食物の消化・栄養の吸収」について学習した後、ゲスト・ティーチャーとして、養護教諭の
先生が話をしました。
みんな、真剣に聞いています。




養護教諭の先生から、
「小腸で吸収された栄養は、血液にのって、全身に運ばれます。手、脚、心臓、脳にも運ばれます。」
「そして、脳に届くのはブドウ糖という栄養だけです。このブドウ糖は、ご飯・パン・めん類・いも等
にたくさんふくまれているデンプンが、消化液によって細かく分解された物です。」
というお話があると、子供たちの中から、
「えっ、脳にも行くの?」
「じゃあ、毎日、朝ご飯をしっかり食べてこなくちゃ!」
という声があがっていました。


学習したことが、日々の生活に生かされるって素敵ですね!!
明日から、しっかり朝ご飯を食べてきましょうね。
ジャガイモ畑の草むしり(6年生)★ 5月27日
6年生は、朝からジャガイモ畑の草むしりです。
ジャガイモの生長と同じく、草も元気に伸び、子供たちは一生懸命にむしっていました。





下校の様子 ★ 5月26日
5月26日(月)
今日は、135名全員登校し、元気に帰っていきました。
明日も元気に登校してくださいね。










今日の給食 ★ 5月26日
【献立】ごはん 牛乳
豚肉のケチャップソース炒め
即席漬け 豆腐スープ

今日も、おいしくいただきました!
氷見市小学校連合体育大会(6年生) ★ 5月23日
さわやかな空のもと、第47回氷見市小学校連合体育大会が高岡市営城光寺運動公園 陸上競技場で
行われました。
6年生全員が参加し、4×100m混合リレー、選手1000m走、選手100m走、全員100m
走、全員60m走の競技がありました。
湖南子は、最後まであきらめず、全力で走り抜き、素晴らしい成績を収めました。
仲間を応援する姿も、さすが湖南子でした。





2年生 算数科の授業 ★ 5月22日
3時間目、2年生は算数科「ひっ算のしかたを考えよう」の学習でした。
これまで学習したことを思い出しながら、2位数ー1、2位数(繰り下がりあり)の筆算の
仕方について考え、自分の言葉で説明していました。


「40-18」は?
一の位が0のときは? ブロックを並べて一生懸命に考えていました。
分からないことは、友達に聞いたり、相談したり姿がみられました。みんな真剣です。

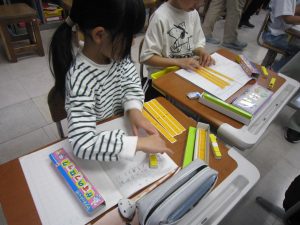
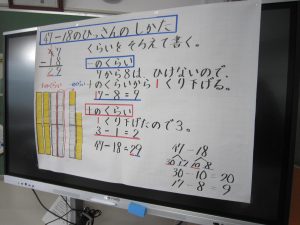


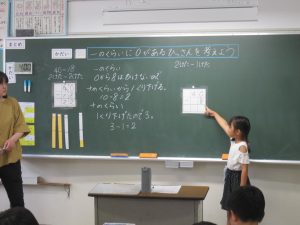
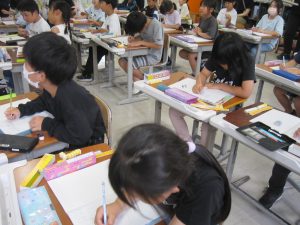
3限目の様子(1年生) ★ 5月21日
氷見市からタブレット端末が貸与されました。
1年生は、初めてタブレットを使った学習をしました。
ルールを守って、大切に使うことができました。これからも、学習に役立てていきます。



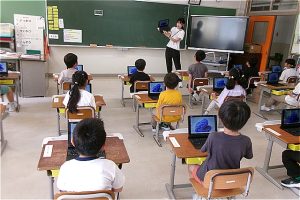

2限目の様子(6年) ★ 5月21日
5月23日(金)氷見市連合体育大会に向け、6年生がハードル走の練習を続けています。
当日、ベストを尽くせるとよいですね。



おいしいお茶を入れました!5年生 ★ 5月20日
今日は、家庭科で、お湯をわかしお茶を入れる学習をしました。
どきどきしながらやかんに水を入れ、ガスに火を付け、お湯をわかしました。
お茶を入れ、小さい和菓子と一緒にいただきました。
「このお菓子、あまくておいしい!」
「あまいお菓子といっしょに、少し苦いお茶を飲むと、すごくおいしいね。」
「家でも、飲んでみたいな。」
家庭科室に、みんなの笑顔が広がりました。




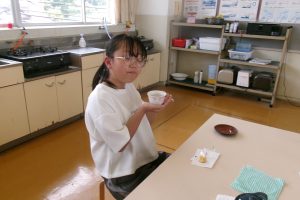

子供たちが入れてくれたおいしいお茶は、職員室の先生達にも届きました。


本当においしかったです!
ぜひ、家でもやってみましょう!!
整理体操~閉会式 ★ 5月18日
6年生をリーダーに、一人一人が主役となり、みんな全力でがんばった運動会。
本当にすばらしかったです。白団、赤団の戦いは、最後まで分かりませんでしたが、
今年は白団の優勝でした。
「なりたい自分」に向かって、ぐんぐん伸びる湖南子の姿に感動の連続。
保護者の皆様、ご来賓、地域の皆様、最後まで温かなご声援、ご協力を
本当に、ありがとうございました。
ゆっくり休み、火曜日には元気に登校してくださいね。









































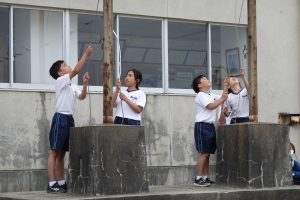




選手リレー ★ 5月18日
今年は、下学年、上学年に分かれて選手リレーを行いました。
力強い走りに、応援にも力がはいりました。





































綱引き ★ 5月18日
5・6年生は、綱引きです。引き分けが2回続きましたが、結果は赤の勝ちでした。
















湖南ソーラン ★ 5月18日
3・4年生の「湖南ソーラン」は、ビシッとかっこよかったです。
動きも、かけ声も息ぴったり!


















チェッコリ玉入れ ★ 5月18日
かわいいチェッコリを踊りながらの玉入れです。
高学年も、一緒に踊っていました。かわいい湖南子です。
なんと、玉入れは、同点でした。


















竹刀体操 ★ 5月18日
5・6年生は、郷土の先賢 斉藤 弥九郎にちなんで、代々引き継がれている竹刀体操
です。勇ましい姿をみせてくれました。


















湖南タイフーン ★ 5月18日
3・4年生は、息をそろえて、湖南タイフーンです。