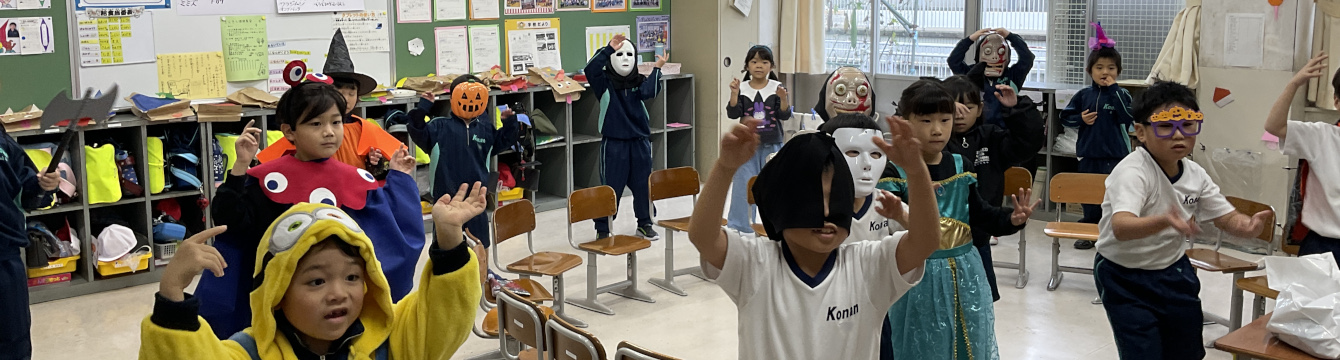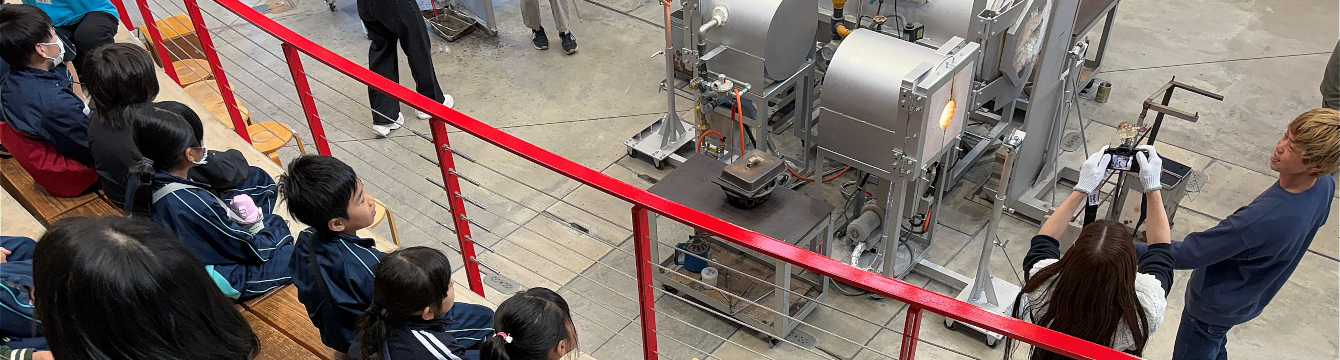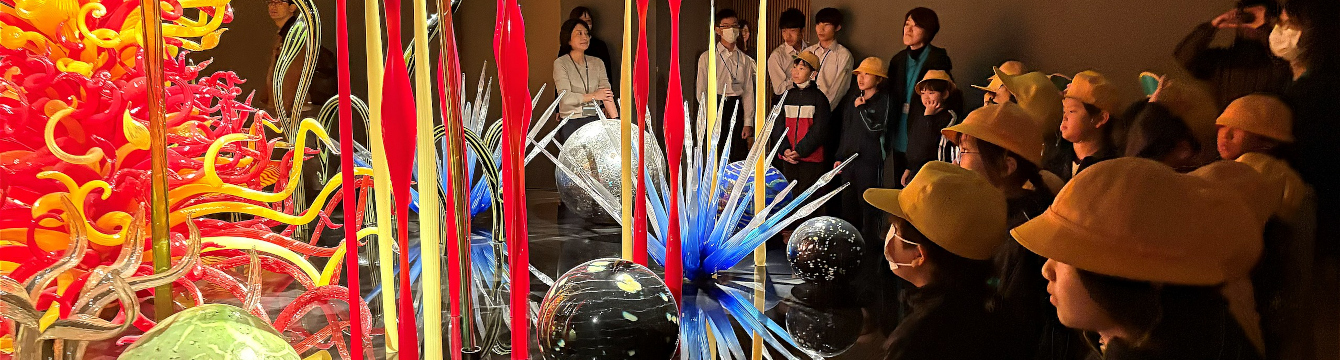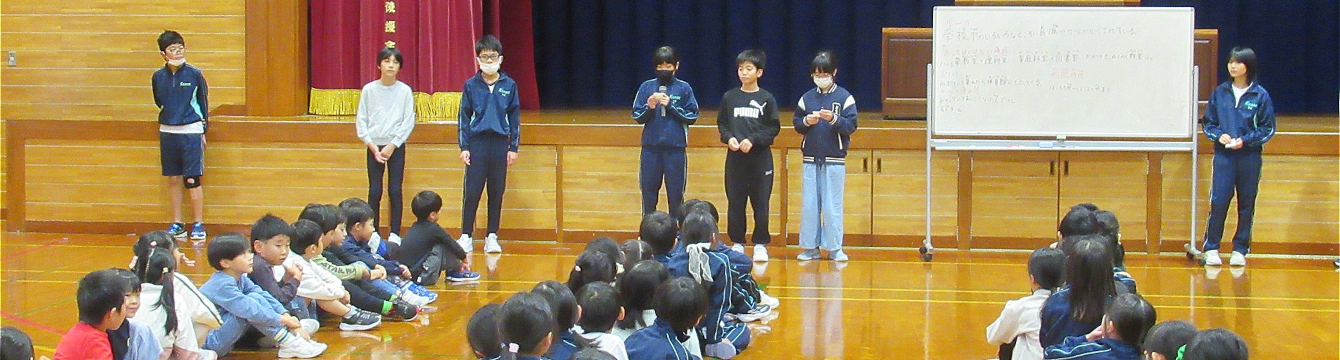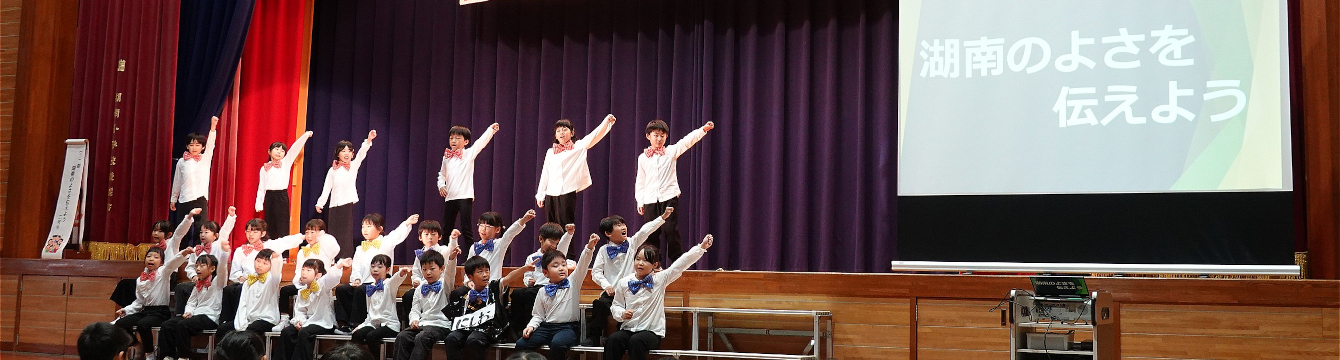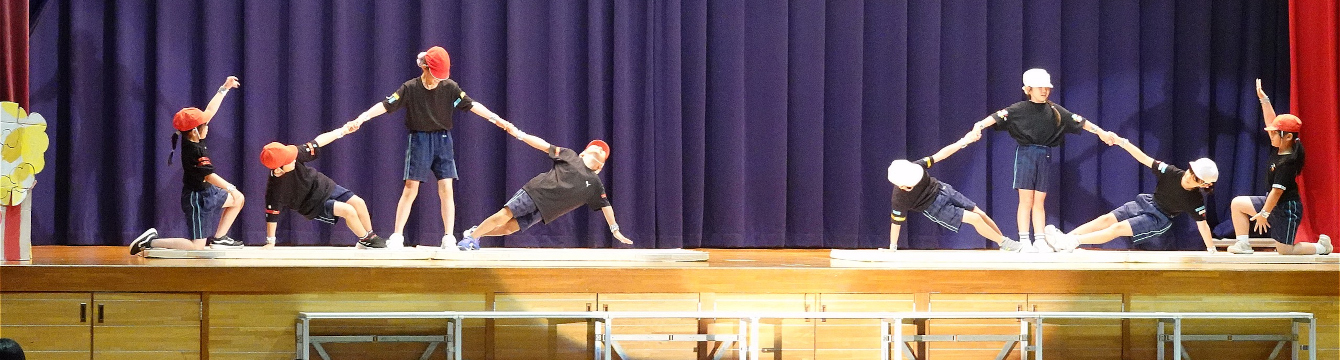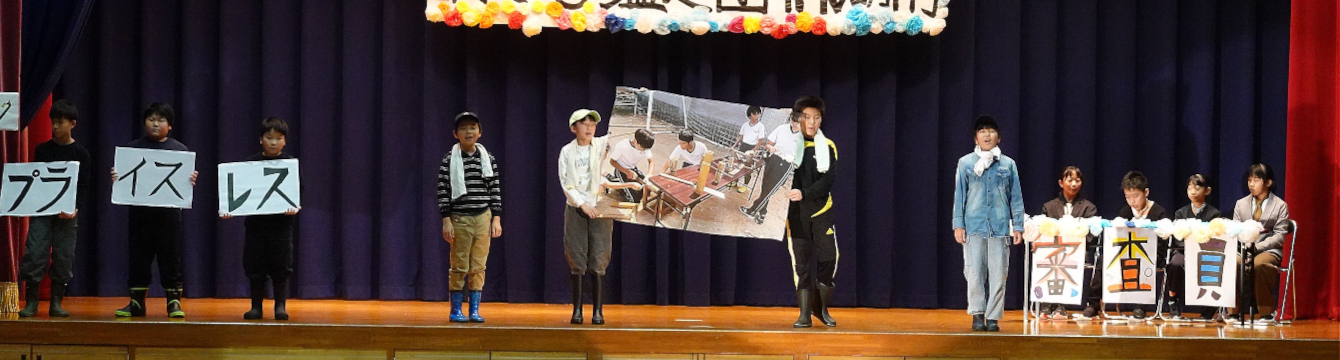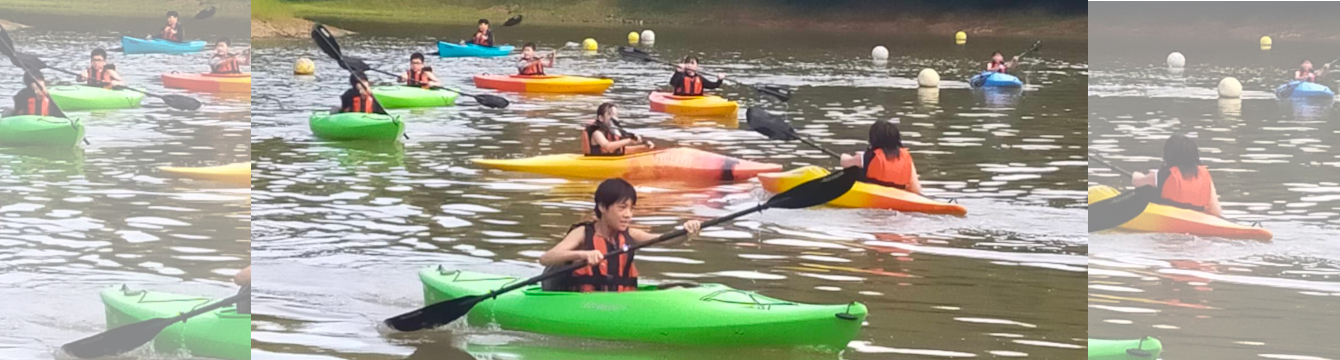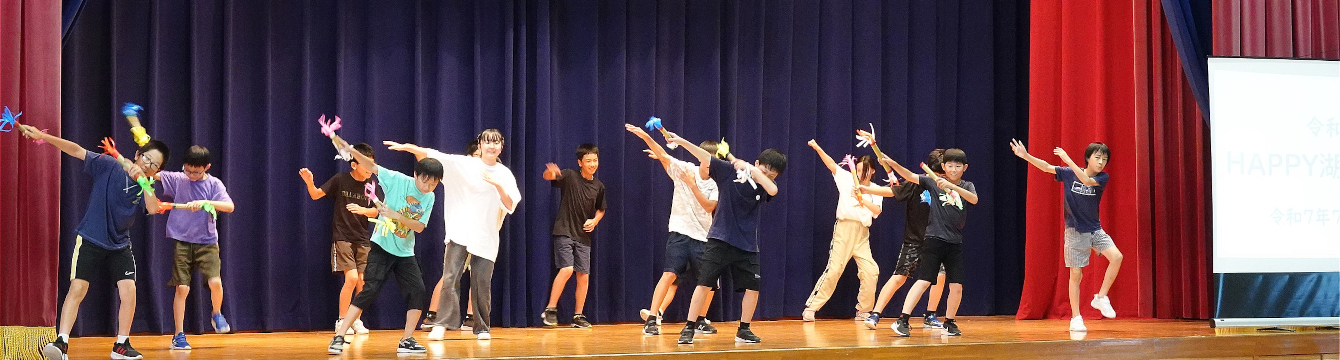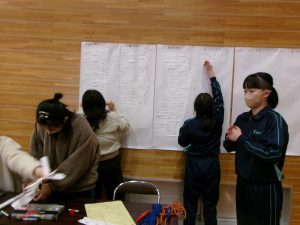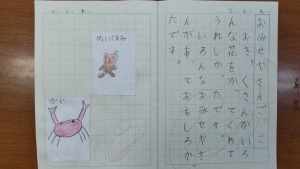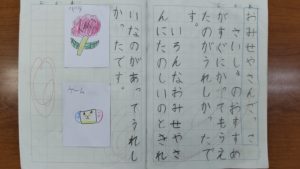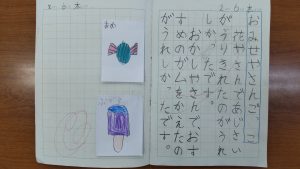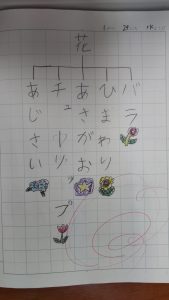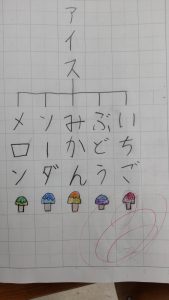本番と同じ気持ちで ~卒業式予行~
14日の卒業証書授与式と同じ時刻に予行を始めました。
本番と同じ気持ちで臨みます。
音楽とともに拍手が沸き上がり、卒業生が入場してきました。
開式の言葉、国歌斉唱の後は卒業証書授与です。
最初から最後まで行いました。
式辞、祝辞、祝電披露の内容は、本番のお楽しみです。
そして、別れの言葉では、
卒業生も在校生もこれまでの練習を思い出し、懸命に取り組みました。
校歌斉唱、閉式の言葉の後、卒業生が退場しました。




つつがなく予行が終わりました。
その後、外で、門出の集いの並び方も確認しました。
今日を含めてあと4日。
予行を行うことで、卒業が一気に迫ってきたように感じました。