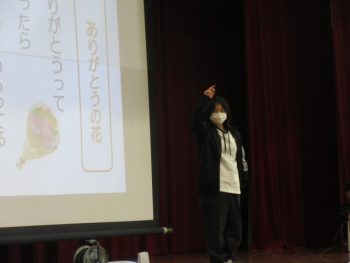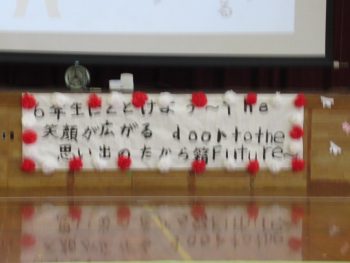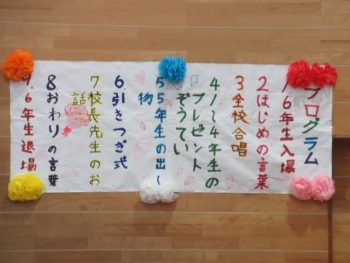今日の4年生 4月18日
4月18日(木)
国語の時間です。
漢字の練習をしました。
電子黒板を使って漢字の書き方を確かめました。


ドリルを使って練習します。


ドリルに向かう表情がりりしく感じました。


ドリルに書いた字を見直して、丁寧に書き直す子供もいました。
このように集中して練習すると、漢字を覚えやすくなりそうですね。
理科の時間です。
校庭で春の植物を見つけてきました。


こんな花がありましたと見せてくれる子供もいました。

教室に戻るとすぐにノートに記録し始めていました。




後から戻ってきた子供もすぐに花をおいて、ノートに記録し始めました。
「絵をかける人は絵で、言葉で記録してもいいですよ」と先生の言葉で、ノートに言葉で記録し始める子供もいました。


「先生がとってきた花を使ってもいいですよ」と、全員が植物を見れるような配慮も見られました。

真剣に、記録していました。