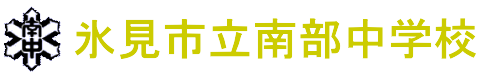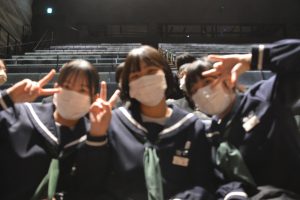今日は、各クラスのコーラスフェスティバル企画委員が集まって、取組の振り返りを行いました。
最初に、①今年度やってよかった取組、②困ったことや課題が残ったことをグループで紹介し合いました。


「他学年との合同練習をしてよかった。来年はもっとやりたい。」
「学級会を行うことで、みんなの思いを聞いたり、具体的な練習方法をみんなで話したりすることができた。」
「音程が取れていないところを自分たちで見つけるのが難しかった。」
などの具体的な意見がたくさん聞かれました。
次に、来年度に引き継ぎたいことについて、意見を出し合いました。


1、2年生は、先輩たちの話を聞きながら、
「自分たちの歌声や表情を客観的に聞いたり見たりするために、タブレットを活用したい。」
「コーラスフェスティバル記録ノートを活用して、振り返りをしたり、メモをとったりしていきたい。」
「記録ノートの記入は、3年生のように帰りの会の前の時間を活用できそう。」
と来年度はこうしたいという熱い思いを語っていました。

今日の振り返りを通して、合唱に対する取組を、上級生から下級生につないでくれたと思います。
これから、南中の合唱がさらに「深化」していくことを楽しみにしたいと思います。