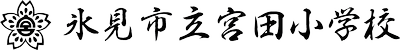運動会
9月12日(土)
運動会
心配された雨もどこへやら、快晴の空の下、運動会を行うことができました。
朝早くから、PTA役員の皆様には、万国旗張り、テント設営等たくさん助けていただきました。
中には、二日連続の作業をしてくださった方もいらっしゃいました。
おかげさまで、きれいに整った会場で運動会を行うことができました。
子供たちは、今年度初めて、みんなが集まっての行事になった運動会を楽しむことができたようです。
その様子を紹介します。
開会式です。

堂々とした選手宣誓でした。
整列の様子。

ソーシャルディスタンスを保って、きれいに並びました。
青空の下、万国旗が映えます。
全校 準備運動。


6年生の体育委員長が分かりやすく説明し、青空の下、体をほぐしました。
1・2年 80m走。

走る人も、見守る人も緊張の一瞬です。
1・2年生の80m走、3~6年の100m走では、どの子供も一生懸命に走りました。
軽やかに走る姿に目を引かれたのですが、それ以上に、他の子供に先に行かれても力いっぱい走る姿に心を打たれました。
5・6年 60mハードル走。

走る5・6年生はリズムよく走り切りましたが、準備をした4年生も上学年の一員として立派でした。
PTA役員の皆様、ご協力をいただきましてありがとうございました。
1・2・3年 「レッツ チェッコリ!みんなで玉入れ」
ここでもPTA役員の方にご協力をいただき、かごを1・2年生でも玉が届く高さに調節しました。



玉入れを投げ入れる前には、かわいらしく軽快に踊りました。
4・5・6年 綱引き

人との間隔をとるために、人数を少なくしました。
その分、一人一人が全力を出しやすくなりました。
紹介しきれませんでしたが、この他にも各競技で、子供たちは勝利を目指して一生懸命に取り組みました。
今年度の優勝は、赤団でした。赤団のみなさんおめでとうございます。
青団のみなさんが団結した姿は、すばらしかったです。
黄団のみなさんの一所懸命な姿は、見ていてすがすがしかったです。
今年度は、午前中だけという、規模を縮小した内容でしたが、感染症及び熱中症への対応を考慮した中で、子供たちにとっても充実感した運動会となりました。
暑い中、新型コロナウイルス感染症防止のためにご配慮いただきながら観覧された皆様に感謝いたします。
※土曜日に、氷見市のコンピュータサーバー入替工事を行いましたところ、予想外の影響を受け、ホームページを更新することができませんでした。情報をお伝えすることが遅くなり、お詫びいたします。