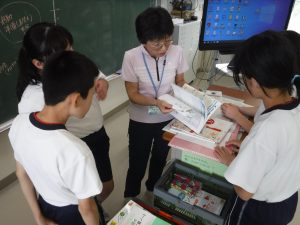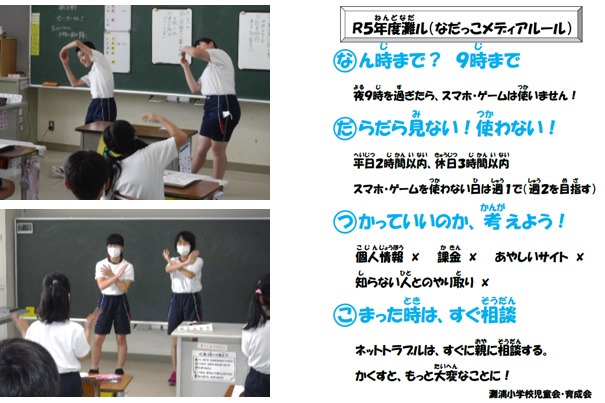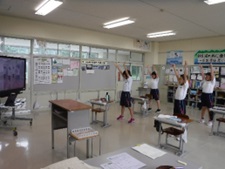水泳学習(7月3日、10日、19日)
今年度から水泳学習は、氷見市民プールの施設を利用して、全校児童で行います。
はじめに、水泳の泳力についてアンケート調査を行いました。
次に、第1回目(7月3日)の水泳学習で実際の泳力をチェックし、本人と相談して自分のレベルに合ったクラスで水泳練習を行いました。
第2回(7月10日)、第3回(7月19日)の水泳学習では、自分の泳力に合わせたレベルのクラスで練習を積み重ねました。
新しい課題にわくわくしながら挑戦したり、泳力の成長を実感して喜んだりする子供の姿が見られました。
夏休みも、市民プールでさらに練習を積み重ね、9月にはクラスがアップできたらいいですね。
頑張ってください。