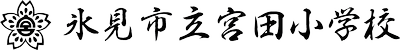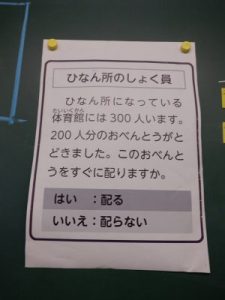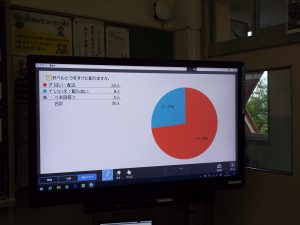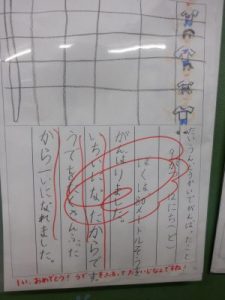4年生 リコーダーの音色
9月28日(月)
4年生 音楽
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、
1学期の間は、歌を歌ったり、リコーダーを吹いたりすることを控え、
工夫しながら音楽の学習を進めてきました。
2学期からは、広い音楽室で、換気を徹底し、友達との距離を取り、
密を避けた状態で、歌やリコーダーの学習を取り入れています。

まずは、リコーダーを持ち、友達と対面にならないように、場所を移動します。
リコーダーを演奏するときだけ、マスクを外します。

この輪になった状態を生かして、「ド」の音を順番にならしていく「ドの音リレー」です。
回ってくるとどきどきしましたが、ぐるりと1周成功しました。

次に、教科書の曲「陽気な船長」を練習します。

スタッカートの付いている部分と、付いていない部分を区別しながら演奏することが、今日の目当てです。
タンギングやリズムに気を付けて演奏をします。
門島先生の伴奏が、だんだん速くなりますが、遅れないで上手に演奏できる子供が増えてきました。
音楽室から、子供の歌声やリコーダーの音が聞こえてくると、
学習を進めることができるようになってきた喜びを感じます。
今後も試行錯誤しながら、学習を進めていきます。