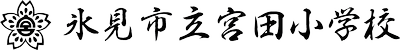万葉の世界に触れて
2月1日(月)
3年 総合的な学習の時間
氷見市教育委員会より学芸員の先生を招いて、3年生がふるさと学習をしました。
学芸員の先生から、宮田小学校校歌の歌詞にある、昔あった田子の浦の場所や広さ、でき方について説明がありました。
今から、6000年前は、海がいろいろなところに入り組んでいたそうです。
次第に砂がたまり、海が大きな湖になり、田子の浦と呼ばれるようになったそうです。
そこに、大伴家持が訪れ、短歌を詠んだ歌碑が泉の杜と、下田子にあると教えてくださいました。

学芸員の先生から、大伴家持に関するクイズが出されました。
第1問
「大伴家持が生きていたら、今年で何歳になるでしょう」

「正解は、1303歳です」

正解した子供から、小さなガッツポーズが見られました。
大伴家持との距離が少しだけ近くなりました。
第2問
「大伴家持は、今の世の中でいうと何になるでしょう」
①「県知事」②「氷見市長」③「富山県の神様」
③を選ぶ子供が多かったです。
越中の守、大伴家持(えっちゅうのかみ、おおとものやかもち)という呼び方から、③の「神様」と考えたのでしょうか。

その後、泉の杜と下田子で詠まれた短歌について説明を聞きました。
泉の杜で詠まれた、
「多胡の崎 木の暗茂に ほととぎす 来鳴き響めば はだこひめやも」という歌と、
下田子で詠まれた、
「藤波の 影成す海の 底清み しずく石をも 珠とぞ吾が見る」という歌が表す場面や
大伴家持の気持ちについて教えていただきました。


1300年前の万葉の世界に触れることができたようです。
近くを通ることがあったら、今日の学習を思い出し、昔の世界に思いをはせましょう。