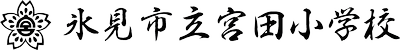宮田っ子のみなさん、元気ですか Vol.4
宮田っ子のみなさん、元気ですか?
登校日で、先生や友達の顔を見てほっとした人もいるのではないでしょうか。
今年は、学校が休みだったので本調子になりにくい人がいるかもしれませんが、4月からの新学期はすぐにやってきます。今のうちから新しい学年(中学校)へ向けての準備をしておきましょう。
みなさんへ向けて先生からの、メッセージ、第4号です。

◯もうすぐ進級。どんな◯年生になりたいか、めあてをもって毎日を過ごそう!
餘茂田先生より
◯「これだけはがんばりたい!!!」という、目あてをもってまい日つづけましょう。いよいよ、2年生。力をあわせて大きくジャンプ!!!先生たちはいつまでも、みんなのおうえんだんです☆
北村先生より
◯みなさん元気に過ごしていますか。これからも、かぜをひかないように、手洗い、うがいをしっかりとして、健康に過ごしましょう。また、新学期の準備も忘れずに!!
谷口先生より
◯次の学年に上がる大切な時間です。安全に楽しくすごしましょう。4月までがんばっているすがたを思いうかべ楽しんでいます。
小竹先生より
◯コロナに負けない強い体をつくろう!早ね、早起き、朝ごはん!
岡本先生より
明日は、「宮田っ子のみなさん、元気ですか Vol.5」です。お楽しみにしてください。