11月14日(火)くもり
今日は2年次教員研修会があり、たくさんの先生方がこられました。
4の2の算数の授業を通して研修会をしました。
下学年の移動図書もありました。たくさん本を読みましょう。
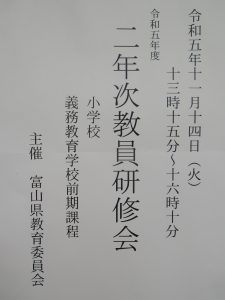










今日は2年次教員研修会があり、たくさんの先生方がこられました。
4の2の算数の授業を通して研修会をしました。
下学年の移動図書もありました。たくさん本を読みましょう。
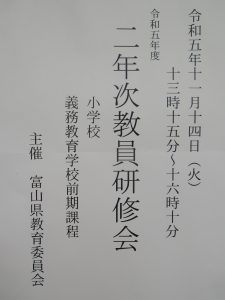











ごはん
ぎゅうにゅう
ぶたにくのにらいため
ブロッコリーのアーモンドあえ
みそワンタンスープ


今日は、肌寒い日でした。
でも、中には半袖の子どももおり、元気に活動していました。
急に寒くなったので、体調管理に気を付けましょう。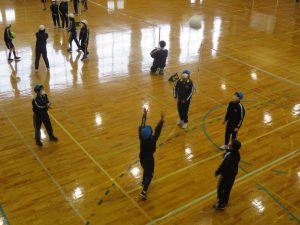

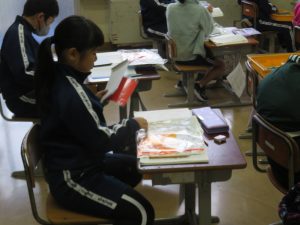






ごはん
牛乳
しいらの南蛮漬け
ほうれん草のごましそあえ
おでん
<ひみの日献立>
今日のおいしい氷見の味は、しいら、ほうれん草、にんじん、こんにゃくです。
今日の南蛮漬けのしいらは、氷見でとれたものです。大きいものは、体長2m、40kgもある、とても大きな魚です。青のグラデーションと金色の斑点があり、虹のように様々な色に見える様子から「虹の魚」といわれているそうです。
おいしい氷見の味を味わって食べましょう。
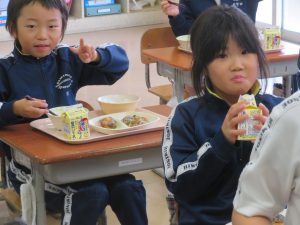



ごはん
ぎゅうにゅう
あじつけこざかな
ポークシューマイ
はるさめのあえもの
ちゅうかコーンスープ


今日は、肌寒い日となりました。
日の暮れるのも早くなりましたので、早めに帰宅しましょう。
1年生が楽しく外国語と触れ合いました。




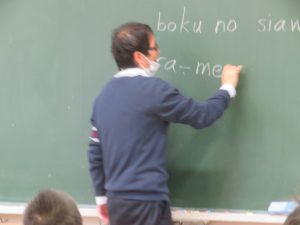



今日は、さわやかな日でした。
3の2は、消防署へ校外学習へ。
6年生は、社会福祉協議会の方と学習をしました。












コッペパン
ぎゅうにゅう
とりにくのマーマレードやき
スパゲティソテー
あきあじシチュー


今日は、先生方の研修会のため12:00に下校となりました。
交通安全に気を付けて、3時までは勉強をしましょう。
明日、元気に登校してください。






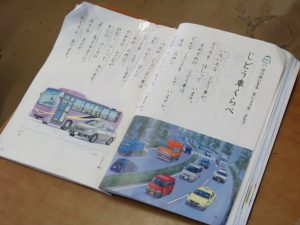



ごはん
ぎゅうにゅう
わふうハンバーグ
くきわかめのきんぴら
なめこじる

