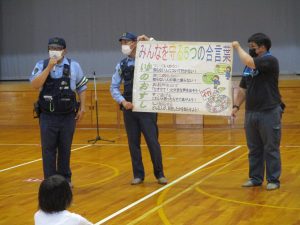第2回親子奉仕活動 (8月20日)
8月20日(土)に、親子奉仕活動を行いました。
例年はグラウンドの除草ですが、貴重な夏休みの土曜日が天候に左右されることなく実施できること、熱中症対策ということから、今年度は校舎の窓ふきに変更しました。
日頃の子供たちの清掃活動では、安全面を考慮して、窓ふきはあまりできていません。
高いところは保護者の方が、低いところは子供たちがと役割分担し、とてもきれいになりました。
また、開始式や閉会式はTeamsを使ってオンラインで配信しました。
子供たちや保護者の皆さんは、エアコンの効いた教室で、電子黒板から育成会長等の挨拶や連絡事項等を確認しました。
早朝6時に各教室に集まり、間隔を取って黙々となどの新型コロナウイルス感染防止対策をしながら、短時間集中で7時には解散しました。
土曜日の早朝の時間帯にもかかわらず、多くの方がご参加され、環境美化にご協力いただきましたことに大変感謝申し上げます。
皆様のおかげできれいな校舎で、気持ちよく2学期を迎えることができます。
夏休みも残りわずかとなりました。体調に気を付けて、お過ごしください。
~ 親子奉仕活動の様子 ~