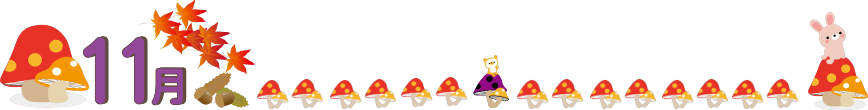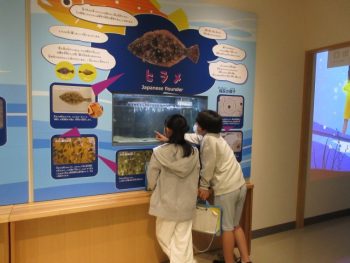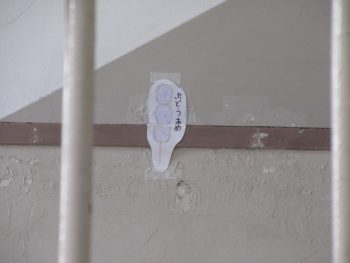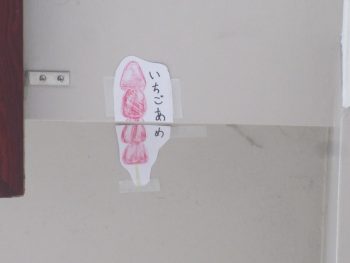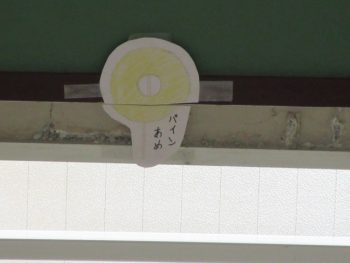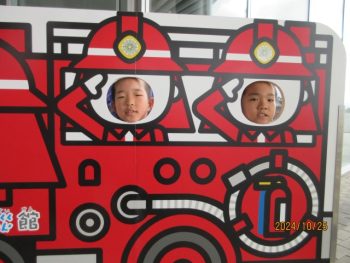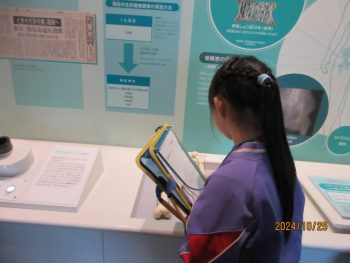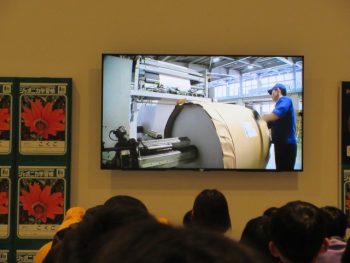今日の2年生 10月31日
10月31日(木)
国語の時間です。
「お手紙」という物語を読んでいます。
今日は登場人物の気持ちを考えました。




怒っている気持ち、悲しんでいる気持ち、いろいろな考えが出ました。
それぞれ、よく聞くとなるほどと納得できる考えでした。


がんばって考えを話していました。
算数の時間が終わりました。


1時間を振り返りました。

先生から、言葉をかけてもらってうれしそうでした。

ほめてもらったことを自信にして、次の学習もがんばりましょう。