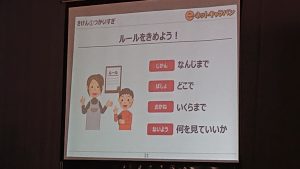あいさつで笑顔いっぱい集会(9月26日)
全校のみんなに、1学期のあいさつカードの結果やあいさつのよさ等について知らせ、もっとあいさつが広がる灘浦小学校にしたいと考え、6年生が「あいさつで笑顔いっぱい集会」を企画し、集会を開きました。
「クイズや劇を入れながらどの学年にも分かりやすい発表にしよう」「ほかほか言葉を使ってぬり絵が完成するようにしよう」など、あいさつを広めるためにいろいろな工夫をしながら、伝えることができました。







「あいさつで心と心をつなぎ、絆が深まったらいいな」という6年生の思いが全校に伝わり、あいさつで笑顔いっぱいの灘浦小学校にしたいですね。