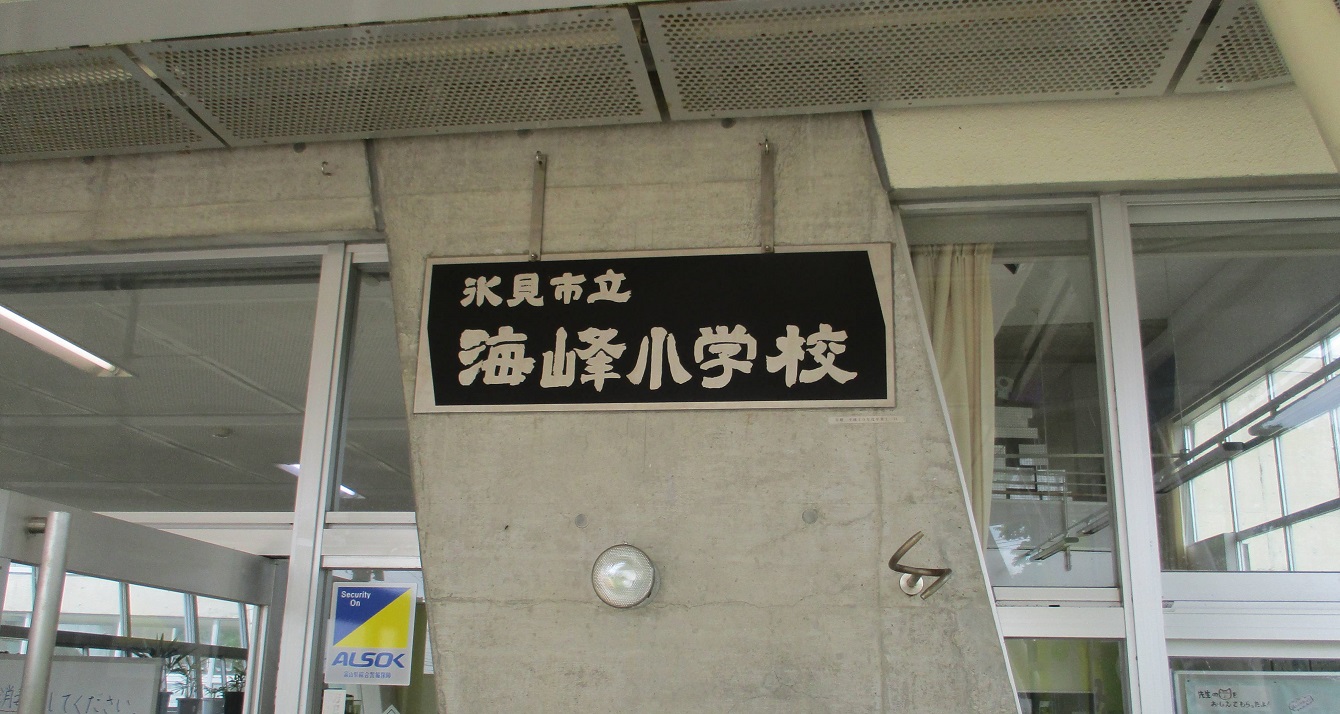寒くても、子供は元気!
3月に入っても、今週はまだまだ寒い日が続いています。
それでも、海峰っ子は元気です。最近は全員が登校する日が続いています。
今日は、昼休みに2年生から4年生の子供たちがグラウンドに大勢集まり、先生も一緒になって「カンけり」が始まりました。私たちからすると、思わず「なつかし~」と言いたくなる遊びですね~。
空き缶一つあればできる遊びで、「子供の頃はよくやったな~」と懐かしく思いながら見ていました。


5時間目に体育館をのぞいてみると、5、6年生が「ソフトバレーボール」をしていました。
なかなかの接戦もあって、白熱した試合をしていましたよ。
「いいよ、いいよ」「おしい、おしい」という言葉をかけ合い、笑顔で楽しく活動していました(^o^)







子供たちは、体を動かして今日も元気に活動しています!